株式会社奥村組を幹事会社として、株式会社淺沼組、株式会社錢高組、前田建設工業株式会社、株式会社松村組の5社で構成するパイルド・ラフト基礎研究会は、現在最も一般的な基礎である支持杭基礎に比べ、合理的で大幅なコストダウンを可能とするパイルド・ラフト基礎構法の実用化を目指して、2年間の共同研究を実施し、その成果として「パイルド・ラフト基礎設計ガイドライン」を共同作成しました。建物規模および地盤条件にもよりますが、本構法を採用することにより、支持杭基礎に比べて基礎工事費の10〜20%のコストダウンが可能となります。今後、研究会構成各社においてこのガイドラインの一層の高度化を図るとともに、同構法の普及を目指していきます。
【研究会構成会社】
株式会社 淺沼組
株式会社 奥村組(幹事会社)
株式会社 錢高組
前田建設工業 株式会社
株式会社 松村組
【パイルド・ラフト基礎とは】
従来、建築基礎構造の設計では「異種基礎併用の禁止」を原則としてきました。しかし、性能設計の導入により併用基礎採用の可能性が高まってきており、その一つの基礎構法であるパイルド・ラフト基礎が注目されています。
建築基準法施行令第38条第4項では、国土交通大臣が定める基準(平成12年国土交通省告示第1347号)に従った構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合、「異種基礎併用の禁止」が適用されないとされており、同告示では、建築基準法施行令第82条の許容応力度等計算を行うことと、有害な損傷、変形及び沈下が生じないことを確かめることとされています。
パイルド・ラフト基礎とは簡単に言えば杭基礎(パイル)と直接基礎(ラフト)の併用で、その両者で建物荷重を支持するものです。支持地盤が深くなるに従い支持杭基礎は高価なものとなりますが、直接基礎と杭を併用して建物荷重を支持するパイルド・ラフト基礎は、コストパフォーマンスにおいて最適な基礎構法です。また、パイルド・ラフト基礎は、直接基礎と同様にある程度の沈下を許容して地盤となじませる基礎形式であることから、支持杭基礎に比べて沈下量は増えるため、ある程度の沈下(数cm程度)が許容される低・中層建物(倉庫、工場、店舗など)の基礎に適した構法です。
【共同研究の概要】
本共同研究では、関東ローム地盤においてパイルド・ラフト基礎の模型試験体による原位置載荷試験(鉛直・水平)および、比較のために同仕様の摩擦杭基礎試験体と直接基礎試験体の載荷試験を実施して試験結果を詳細に検討し、荷重―変位関係・杭と直接基礎の荷重分担率の変化など、その特性を把握するとともに、これらの試験結果を基に鉛直荷重解析法および、水平荷重解析法の妥当性を検証しました。また、これらの解析法を用いて実建物を想定した建物の試設計を実施し、支持杭基礎・直接基礎および摩擦杭基礎など他の基礎構法とのコスト・性能比較を行って、パイルド・ラフト基礎構法の有効性を確認しました。これら一連の研究成果を、「パイルド・ラフト基礎設計ガイドライン」として取りまとめました。
【設計ガイドラインの概要】
パイルド・ラフト基礎は、建物規模および地盤条件により、支持杭基礎などの基礎構法に比べて大幅なコストダウンが可能となる合理的な基礎構法です。
しかし、「建築基礎構造設計指針(2001)」:(日本建築学会)に示されているパイルド・ラフト基礎は、直接基礎として性能を満足し、沈下抑制として杭を追加する場合を対象としており、杭と直接基礎の荷重分担を考慮したより合理的な設計は、実験・解析などに基づく検討による必要があるなど、限定されたものでした。
今回の共同研究の結果、直接基礎として支持力が不足したとしても、摩擦杭を併用することにより不足分の支持力を確保するとともに、沈下も抑制することが可能となりました。
本ガイドラインでは、全体の設計フローとともに、実験結果に基づく簡易解析法(鉛直荷重解析および水平荷重解析)を示し、これらの解析法を用いた試設計例と、他の基礎構法とのコスト・性能比較を示しています。
【今後の展開】
研究会構成各社では、本ガイドラインの有効活用により、コストパフォーマンスにおいて最適なパイルド・ラフト基礎構法の普及を図るとともに、実施工を通じて設計ガイドラインの一層の高度化を目指して行く予定です。
以 上
【お問い合わせ先】
株式会社奥村組
技術本部 技術研究所
秦 Tel .0298-65-1830 |
◆パイルド・ラフト基礎概念図
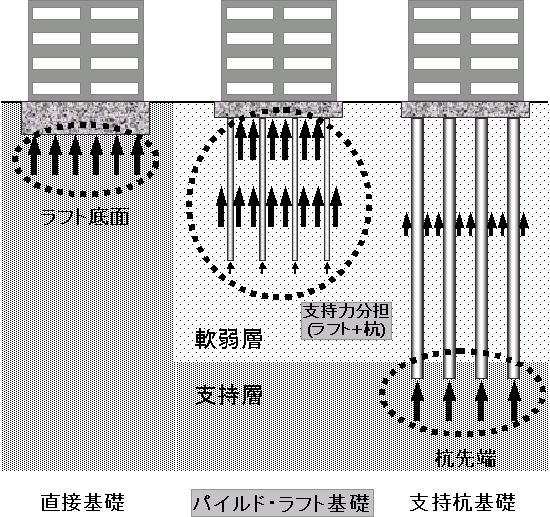
パイルド・ラフト基礎概念図
◆原位置載荷試験状況

鉛直載荷試験

水平載荷試験
|
